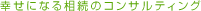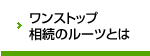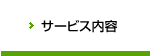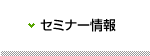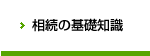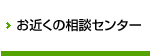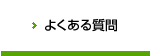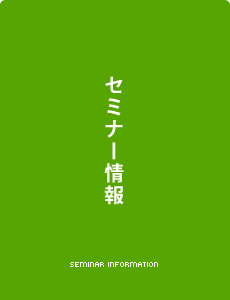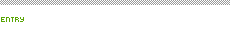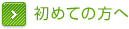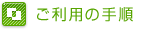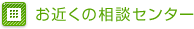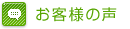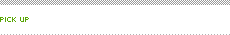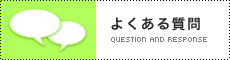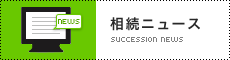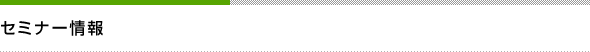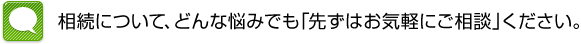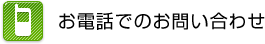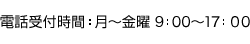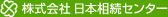11月号「『人生100年時代』の備え」
2025.11.04 
先月の相続ニュースでもお伝えしましたが、日本社会では、超高齢化・多死社会へと構造が変化し、「人生100年時代」といわれるように100歳まで生きることは珍しいことではなくなってきています。実際に、2025年9月1日時点の住民基本台帳に基づく100歳以上の高齢者数は、前年より4644人増加し、9万9763人となり、100歳以上の人口は55年連続で増加しています。内訳は、女性が全体の88.0%を占めており、女性が男性より圧倒的に長生きをしています。
「人生100年時代」と併せて、「長生きのリスク」という言葉もよく聞くようになりました。これは、長生きをすればするほど「経済的なリスク」がある、つまり生きるためのお金(生活費、医療費など)がかかるということです。現役時代から貯蓄していた方でも、年金だけでは暮らせない方が多く、これまでの貯蓄を取り崩して生活してきたけれども、長生きすればするほどお金が足りなくなってくるという不安が生じます。
最近では、つみたてNISAやiDeCoなどの長生きに備える商品が多くなってきましたが、物価も上昇している今ではお金に働いてもらう必要性を感じていらっしゃる方も多いと思います。
今回の相続ニュースでは、「長生きのリスク」の経済的リスクに備える部分については、別にお話するとして、長生きをする際の「判断能力低下のリスク」、いわゆる認知症対策についてお伝えします。
なぜ、認知症対策が必要かと言いますと、認知症と診断されてしまうと、財産が凍結してしまうという点にあります。つまり、本人が認知症と診断されると、何ら対策を講じていなければ、預貯金の引出しや解約、不動産の売却やアパートなどの収益物件の管理ができなくなってしまいます。なぜなら、これらの行為は法律行為だからです。認知症と診断されてしまうと、本人はもはや法律行為をすることができず、本人の家族が日常に必要な費用を立て替えて支払うなどの負担強いられることになります。
そこで、認知症対策の基本としては、「任意後見制度」と「家族信託」という制度を利用することが考えられます。「任意後見制度」については、詳しくは、今年の4月号相続ニュースをご参照ください。
「家族信託」は、委託者(財産の管理を託す人)である本人と、受託者(財産の管理を託される人)である家族、受益者(通常、本人)のために信託財産の管理を受託者に託すという内容の契約を締結します。例えば、高齢の親(委託者)が子ども(受託者)に、自分の認知症対策として、自宅や自分の預金の管理を託すことで、認知症になった場合でも、財産が凍結することを回避することができます。なお、自分の財産のうち、どの財産を信託契約で管理してもらうかについては、家族信託の契約書にて、具体的な契約内容を自由に決めることができます。
ただし、いわゆる「おひとりさま」の場合は、親族などのサポートを受けることが難しいのがほとんどなので、家族信託を利用することが難しいのが現状です。このような場合には、信頼できる第三者に財産管理を依頼するという「任意後見制度」を活用することが考えられますし、信託会社や信託銀行などの商事信託などの利用も有効です。
これらの対策ができるのは、判断能力が低下するまでの間のみです。時間が経てば経つほど不利になってきますので、早めの行動が大切です。何から始めたらよいのかお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
ワンストップ相続のルーツ
代表 伊積 研二