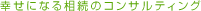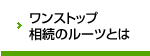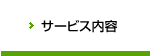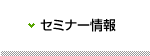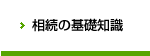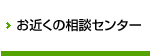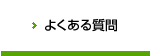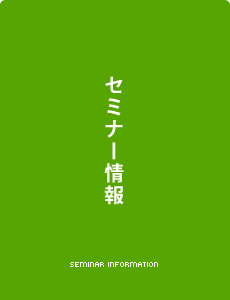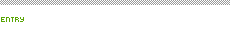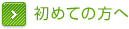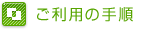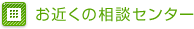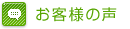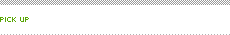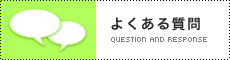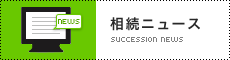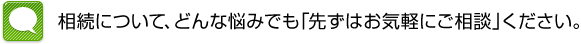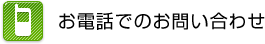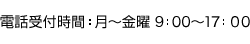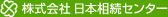2月号「貸付用不動産の評価方法の適正化」
2026.02.02
昨年12月26日、令和8年度税制改正大綱が閣議決定されました。このうち、今回の相続ニュースでは、貸付用不動産の評価方法の適正化についてご紹介いたします。
今回、相続税法の時価主義(相続税法第22条;財産の評価を原則として相続・贈与発生時点(課税時期)の時価で行う原則。)の下、貸付用不動産の市場価格と相続税評価額との乖離が生じている実態を踏まえ、その取引実態等を考慮した見直しが行われます。
① 被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金銭によって評価する。
(注)「課税時期における通常の取引価額に相当する金銭」については、課税上の弊害がない限り、被相続人等が取得等した貸付用不動産に係る取引価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって評価することができることとする。
② 不動産特定共同事業契約又は信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定のものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産については、その取引の時期にかかわらず、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
(注)「課税時期における通常の取引価額に相当する金銭」については、課税上の弊害がない限り、出資者等の求めに応じて事業者等が示した適正な処分価格・買取価格等、事業者等が把握している適正な売買実例価額又は定期報告書等に記載された不動産の価格等を参酌して求めた金額によって評価することができることとする。ただし、これらに該当するものがないと認められる場合には、上記①に準じて評価(取得時期や評価の安全性を考慮)する。
なお、上記の改正は、令和9年1月1日以後に相続等により取得する財産の評価に適用されます。ただし、上記①の改正については、当該改正を通達に定める日までに、被相続人等がその所有する土地(同日の5年前から所有しているものに限る。)に新築をした家屋(同日において建築中のものを含む。)には適用されません。
この改正により、相続開始前5年以内に取得または新築された貸付用不動産については、取引価額等を基礎とした時価により評価されることになります。したがって、相続対策としてのアパートなどの資産の取得等は、できるだけ早めに取り掛かり、長期間保有することで節税効果が得られることになります。
相続対策を行う際には、できるだけ早く取り組むことが得策です。どのような対策が有効かについては、家族構成や資産状況により異なってきます。まずはお気軽にご相談ください。
ワンストップ相続のルーツ
代表 伊積 研二