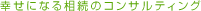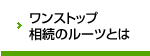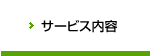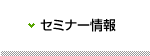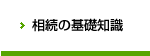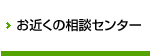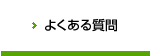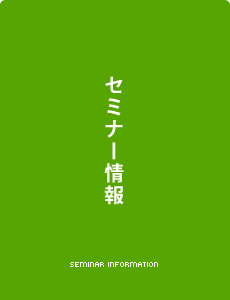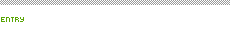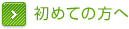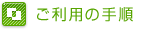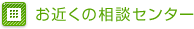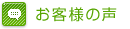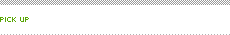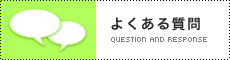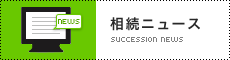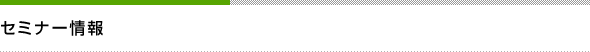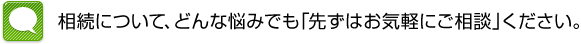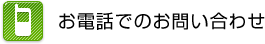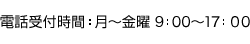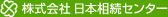9月号「認知症になる前に」
2025.09.01 
超高齢化社会、人生100年時代の到来とともに、検討しておいた方がよいこととして、長生きのリスク、認知症のリスクが挙げられます。認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、2024年1月1日に「認知症基本法」が施行されましたが、ご自分の意思を最後まで反映させるためには、やはり早めの対策が必要です。今月号では、認知症になる前にしておいた方が良いことについてご説明します。
検討した方が良い事項としては、まず現状を把握し、今後どのように過ごしたいのか、最後はどのように迎えたいのかを予めプランニングし、実現方法について具体的に検討すること、そして重要なのは財産の管理方法について検討するということが挙げられます。
①財産の把握(プラスの財産・マイナスの財産、どこにあるのか)
被相続人が亡くなり相続が開始すると、相続人は、悲しみのなかお葬儀など故人とのお別れをするとともに、相続税が発生するか否かにかかわらず、相続手続きや遺産分割協議のために、財産目録を作成するなど、財産の調査を行わなければなりません。特に、相続税申告が必要な場合には、相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告及び納税をしなければなりませんので、財産の把握は早い方が有利です。
具体的には、プラスの財産(預貯金、現金、有価証券等の金融資産、不動産など)とマイナスの財産(借入金、保証債務、未払金など)を把握し、できれば生前に預貯金の預け先やローンなどの借入先などは具体的に把握されておいた方が良いと思います。
なお、プラスの財産よりもマイナスの財産が大きい場合には、相続放棄や限定承認などの手続の期限が相続開始から3か月以内なので注意が必要です。
また、近年では、ネット銀行やネット証券などの「デジタル資産」やオンラインショッピングの「未払い債務」などのデジタルサービスを利用する人が多くなっています。このような資産や債務を調べるためには、本人が設定したIDやパスワードが必要です。そのような情報は、本人が家族に伝えていない場合は、いざというときに困りますので、何らかの工夫をして家族が分かるようにしておくことが大切です。
②ライフプランニング(医療・介護・最期はどこで迎えたいか(終のすみか))
お元気なうちに、どのような医療や介護を受けたいのか(在宅医療など)についても検討しておくことが大切です。さらに具体的には、自宅で医療や介護を受けるのか、施設に入るのか、施設でお世話になる場合の必要な資金などについても検討されておく必要があります。
また、ご自分がもしもの時にどのような医療を望むのか(終末医療)、最期はどこで迎えたいのかについても検討しておいた方が、ご家族が悩まれなくて済むので検討していただきたい事項の一つです。
③財産凍結対策(成年後見制度・任意後見制度・家族信託など)
認知症と診断されてしまうと、判断能力が問題とされ、これまでのように自由に法律行為ができなくなります。そうすると、財産が凍結状態になってしまい、これまでのように自由に預貯金を下ろしたり、不動産を売却したり、遺言書を作成することができなくなります。したがって、そのような状態になる前に、財産管理の方法をどのようにするのかについて検討しておく必要があります。
具体的には、法定後見制度を利用するのか、任意後見制度や家族信託などの方法を利用するのか、ということです。身近に財産管理を任せたい方がいらっしゃる場合には、任意後見制度や家族信託を利用することができますが、そうでない場合には法定後見制度を利用することになります。なお、「認知症」によって成年後見制度を利用するケースが最も多く、全体の約6割を占めているようです。
このように、認知症と診断されると、判断能力がないとして、生前贈与や遺言作成などの相続前の対策ができなくなります。そうなってしまう前に、相続対策はお元気なうちに取り組んでいただきたいものです。また、特に前記②や③を実現するためには、ご家族の協力が必要になる場合もありますので、ご家族と一緒に話し合っておくことが大切です。
何をどのようにしたらいいのか分からないとお考えの方は、お気軽に当センターまでご相談ください。ご相談は無料です。
ワンストップ相続のルーツ
代表 伊積 研二