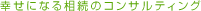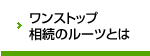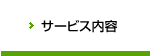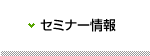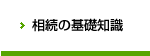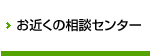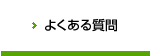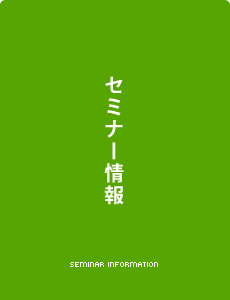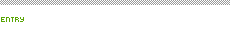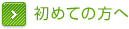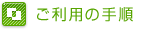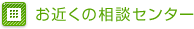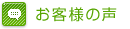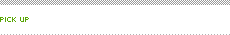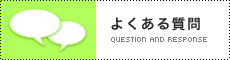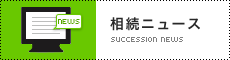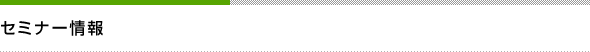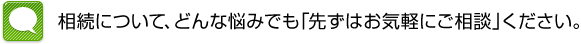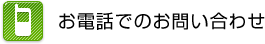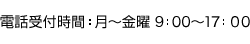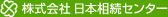5月号「特に遺言書を作成しておいた方が良い場合」
2025.05.01 
相続手続きを行う中で、遺言書があれば、残された相続人の負担を軽減する場合が多いと常々感じます。今回の相続ニュースでは、2022年4月号でもお伝えした内容ではありますが、遺言書作成の重要性を改めて感じたためお伝えします。
まず、遺言書がない場合の主な相続手続きの流れですが、①死亡届の提出(死亡後7日以内)、②相続人の確認、③財産・債務の調査、④相続放棄又は限定承認の申述(死亡の事実を知った日から3か月以内)、⑤遺産分割協議(期限はありませんが、相続税申告がある場合には早期に成立するのが望ましい。)、⑥相続税の申告・納税(死亡の翌日から10か月以内)。⑦不動産等の財産の名義変更(遺産分割協議が終了した後、相続登記については義務化されたため相続の事実を知ってから3年以内に行わなければならない。)という様々な手続きを行う必要があります。
相続手続きで一番大変なのは、遺産分割協議です。例えば、相続人が遠方にいる場合、親子関係が心理的・物理的に疎遠な場合、相続人が仕事をしている場合、財産が少なく分けづらい場合、被相続人が会社の経営者や個人事業主の場合などは、財産等の分け方について話し合い自体がうまくいかないこともあります。また、相続人間の関係が悪い場合は争いに発展し、家庭裁判所で調停・審判を経なければならないこともあります。
これに対し、遺言書があれば、遺産分割協議の手続きが不要になるため、これらの経済的・精神的な負担が軽減されることになります。ただし、あくまで内容的に不備のない遺言書であればの話です。
遺言書は、残された家族への愛情を形で遺すものです。
次の場合に当たる方は、お早めに遺言書を作成しておくと安心です。
〈遺言書が特に必要な場合〉
① 子どもがいない場合(特に親がいない場合は兄弟姉妹に相続権が発生するので注意。)
② 内縁の妻がいる場合(民法上の配偶者として保護されないので注意。)
③ 相続人がいない場合(特別縁故者もいない場合、国庫帰属等になるので注意。)
④ 家族関係が複雑な場合(疎遠・絶縁などは遺産分割協議が難航するので注意。)
⑤ 財産が少ない場合(不動産が多くを占める場合は分けづらいので注意。)
⑥ 会社経営者や個人事業主の場合(事業の財産を複数の相続人に分けてしまうと事業継続困難になるお それがあるので、特定の人に承継させたい場合には承継先・方法に注意。)
⑦ 相続人、特に子どもが遠方にいる場合(遺言執行者の指定を専門家に指定しておく等の配慮が必要。)
なお、遺言書の形式的・内容的確実性を確保するためにも、当センターとしては、公正証書遺言の作成をお勧めしております。
何をどのようにすればいいかお悩みの方は、まずは当センターまでお気軽にご相談ください。
ワンストップ相続のルーツ
代表 伊積 研二