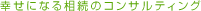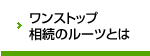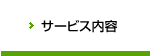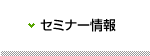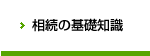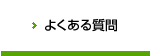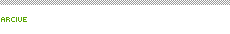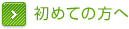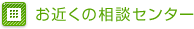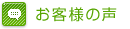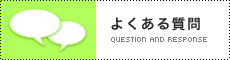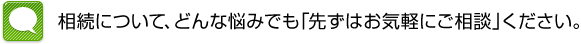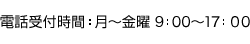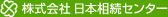2月号「令和3年度税制改正大綱」について
2021.02.01
昨年12月21日に、「令和3年度税制改正大綱」が閣議決定されました。今回の相続ニュースでは、この改正大綱のうち、相続対策や事業承継対策に関わる改正案について、主な内容をご紹介します。
1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等
(1)令和3年4月1日から同年12月31日までの間に、良質な住宅用家屋(耐震、 省エネ又はバリアフリーいずれかの性能を満たす住宅用家屋)の新築等に係る契約締結に関し、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額が、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の契約分の非課税限度額と同額まで引き上げられます。
・消費税等の税率10%が適用される住宅用家屋の新築等の場合の非課税限度額
現行1,200万円→改正案1,500万円
・上記以外の住宅用家屋の新築等の場合の非課税限度額
現行800万円→改正案1,000万円
※なお、良質な住宅用家屋ではない一般の住宅用家屋に係る非課税限度額については、上記それぞれから500万円を減じた額になります。
(2)受贈者が贈与を受けた年分の所得税の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り床面積要件の下限が引き下げられます。
現行50㎡以上→改正案40㎡以上
(3)特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制 度の特例についても、床面積要件の下限が引き下げられます。
現行50㎡以上→改正案40㎡以上
2.直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長・見直し
次のとおり内容を見直した上で、適用期限令和5年3月31日まで2年延長されます。
(1)信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、その死亡の日までの年数にかかわらず※、同日における管理残額(=非課税拠出額-教育資金支出額)を、受贈者が当該贈与者から相続により取得したものとみなされます。現行では、信託設定期間中に受贈者が死亡した場合において相続税が課されるのは、3年以内の贈与に限定されていますので、課税対象が拡大することになります。
ただし、その死亡の日において受贈者が、
①23歳未満である場合
②学校等に在学している場合
③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
のいずれかに該当する場合は除かれます。
(2)上記(1)の場合により相続等により取得したものとみなされる管理残額につき、贈与者の子以外の直系卑属に相続税がかされる場合には、当該管理残額に対応する相続税が、相続税額の2割加算の対象となります。現行では、残額に係る相続税額に2割加算の適用がなされていないので、こちらもやはり課税対象が拡大することになります。
※なお、上記(1)(2)の改正は、令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用されます。したがって、令和3年3月31日までに行った贈与については、贈与時死亡時の取扱見直しの適用対象外となります。
3.直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長・見直し
次のとおり内容を見直した上で、適用期限が令和5年3月31日まで2年延長されます。
(1)贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額(=非課税拠出額-結婚・子育て資金支出額)につき、当該贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税が、相続税額の2割加算の対象とされます。
(2)民法の成年年齢引き下げに伴い、受贈者の年齢要件の下限を18歳以上(現行20歳以上)に引き下げられます。
※(1)の改正は、令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用、(2)の改正は、令和4年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用されます。
4.事業承継税制(非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例措置)
非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例措置につき、次に掲げるいずれかに該当する場合には、後継者が被相続人の相続開始の直前において特例認定承継会社の役員でないときであっても、本特例措置の適用を受けることができるようになります。
①被相続人が、70歳未満(現行60歳未満)で死亡した場合
②後継者が、経営承継円滑化法施行規則の規定により都道府県知事の確認を受 けた特例承継計画において、特例後後継者として記載されている者である場合
以上が相続対策や事業承継対策に関わる改正案の概要です。
生前対策として活用されうる上記1については内容が拡充されるのに対し、2及び3は適用期限が延長されますが、改正案では、例えば教育資金の一括贈与をした祖父が亡くなった際に孫が贈与された教育資金を使いきれていなかった場合には、3年以内の贈与であるか否かにかかわらず、その残額に対して相続税が課され、しかも2割加算されてしまいますので、注意が必要です。2及び3の非課税措置を利用した贈与を検討されている方は、改正前の贈与をおすすめいたします。
通常、改正案大綱はおおむねそのままの内容で税制改正の素になりますが、今後も引き続き改正案の動向に注目したいと思います。
ワンストップ相続のルーツ
代表 伊積 研二